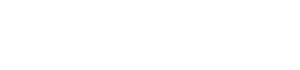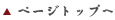HOME > うなぎ料理へのこだわり > うなぎあれこれ
1.うなぎの生態
(1)うなぎは一般に淡水魚として知られていますが、実は海で産卵・孵化を行った後、淡水にさかのぼっていくという生活形態をとっています。
(2)卵から孵化した仔魚はレプトケファルスと呼ばれ、扁平で柳の葉のような形をしています。レプトケファルスは成長して変態し、円筒形の体へと形を変え稚魚(シラスウナギ)になります。
(3)シラスウナギは黒潮に乗って生息域の東南アジア沿岸にたどり着き、川をさかのぼります。
5~10数年かけて成長し、再び海へ戻って産卵した後、一生を終えます。
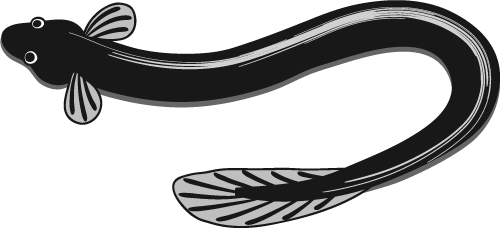
2.うなぎの栄養価
(1)うなぎには、ビタミンA・B群・D・E、カルシウムなど体に必要な栄養素が豊富に含まれています。
(2)また、脳の働きを活発にするDHA(ドコサヘキサエン酸)や、脳梗塞や心筋梗塞等血管の病気の予防に効果のあるEPA(エイコサペンタエン酸)なども含まれています。
(3)しかも低カロリーで、まさに理想的な食品のひとつといわれています。

3.土用の丑の日について
(1)土用の丑の日とは
土用とは、古代中国で考えられた陰陽五行説に基づき割り当てられた期間で、立春・立夏・立秋・立冬それぞれの前18~19日間がこれにあたります。
よって、各季節ごとにある土用期間において丑の日が12日に一度回ってくるわけですから、土用の丑の日というのは、実は夏だけでなく1年間に複数存在しています。
(2)うなぎを食べる由来
諸説ありますが、江戸時代に平賀源内が発案したという説が最もよく知られています。
とあるうなぎ屋が夏に売れないうなぎを何とか売るために源内のところへ相談にいったところ、源内は「丑の日に『う』の字がつく物を食べると夏負けしない」という民間伝承からヒントを得て、「本日丑の日」と書いて店先に貼ることを勧めました。
すると、物知りで有名な源内の言うことならということで、そのうなぎ屋は大変繁盛しました。その後、他のうなぎ屋もそれを真似るようになり、土用の丑の日にうなぎを食べる風習が定着したということです。

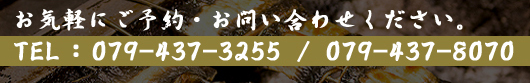
うなぎ料理をはじめ会席料理、一品料理、お持ち帰りメニュー等、
すべてのお料理につきまして、ご予約が必要でございます。
【営業時間】
お昼の部:11:30~13:00 夜の部:現在休業中です
〒675-0126 兵庫県加古川市別府町本町1-8 TEL:079-437-3255 / 079-437-8070
COPYRIGHT(C)2025 将棋屋 ALL RIGHTS RESERVED.